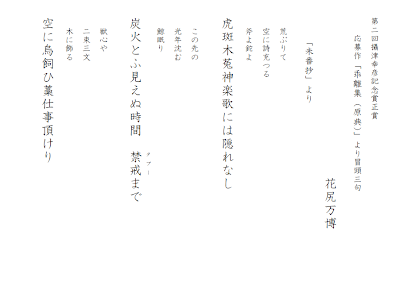先日、三〇年以上の長きにわたって放送されてきたテレビ番組「笑っていいとも!」の終了が発表された。このニュースを目にしたとき、ふいに思い出されたのは、同番組を主題にした映像作品「ワラッテイイトモ、」に対する椹木野衣の次のような言葉であった。
本作は、作者が引きこもっていたころ、唯一の現実との接点であったテレビ映像の記録を、日記として再構成したものだという。
浮かんで来るのは、明け方近くまで一人、部屋で起きていて、夜が白む頃ふとんに入ると、目がさめるのは昼前という「気分」のようなもの。時計の表示は11時58分。テレビをつけるといつものように「笑っていいとも!」が始まろうとしている。そして12時00分。いつものように、それは始まる。(「このうすら寒い夏の正午に」『美術になにが起こったか』国書刊行会、二〇〇六)
学校を休んだ日、布団から出て何気なくテレビをつけるといつも「笑っていいとも!」が流れていたような気がする。画面では花束と花輪をどっさりと並べた席で特に何ということのないお喋りが続く。CMが明けると段取り通り観客の拍手があり、アイドルや芸人たちがだらだらとゲームに興じている。それでも「笑っていいとも!」を観ていたのはどうしてだったろう。「笑っていいとも!」は、僕にとって、学校を休んだ日のあの浮き足立つような喜びと、少しばかりの後ろめたさと、世界から取り残されてしまったような気重さとともに呼び起されるものだ。思えば、僕が「笑っていいとも!」を観ていたのは、きっと、「笑っていいとも!」を今日もまた見ているであろう人たちと繋がるためであったような気がするのである。いわば、どうにも身動きのとれない場所から、それでも世界に繋がろうとしたときに、もっとも容易く手に入る補助線こそ「笑っていいとも!」なのであった。僕は「笑っていいとも!」を観ることで、今日もまたいつも通りであるはずの世界に、僕もまたいつも通りに参入してよいのだという手応えを得ていたのである。
でも僕はいつのまにか「笑っていいとも!」を観なくなってしまった。それはたぶん、世界を想起するための補助線となるものが、いつのまにか他のものへとすり替わってしまったからだろう。思えば、傲慢な僕はもっと僕仕様の補助線を求めるようになっていたのではなかったか。多分に逆説的だが、世界は前提ではなく、僕仕様の補助線の向こうに想起されるものであるような気がしたのである。
*
青木亮人が評論集『その眼、俳人につき』(邑書林)を上梓した。同書において井上弘美がとりあげられていることを疑問に思う俳人は、きっといるにちがいない。それは自らを少数派と認め、それを矜持としながら俳句史のなかに自らの座標を定めてきた者であろう。彼らには井上弘美の句集について論じる必要はないし、だからこそ、彼らは井上を読み、論じるための方法論を持つこともないのである。だが青木は、たとえば「転勤」と前書された井上の句「春の暮教室に鍵かけて出づ」を次のように読む。
教師の「転勤」(多くは三月であろう)を季語「春の暮」で表現した点、またそれを「教室に鍵かけて出づ」と具体的な動作で示した点に工夫があるのは無論であるが、むしろ「春の暮(の)教室」から想起される情景に、つまり夕陽が射しこむ教室の静けさが感じられるところに同じ教員として胸を打たれてしまう。
私自身に引きつけると、中高一貫校とはいえ生徒との付き合いは基本的に一年である。クラスが変わり、担当も変更すれば彼らとの関係は稀薄にならざるをえない。もちろん、その後も廊下で会えば挨拶をしあうし、ラウンジで世間話をすることもあるが、何か大切なものが過ぎ去った後の余韻という感じであり、彼らの読書ノートを見る機会もほぼ消えるのであった。(略)三学期を終えたある日、彼らの座席には夕暮れの光が漂い、その机や椅子は墓碑のように宵闇に沈みゆくのだった。(「卒業、グランドピアノに映る青空」)
井上の句に対する青木の読みのありようは多分に私的であるが、しかし井上の句とは、そのような読みによってはじめて生き生きとしたものとして発見されるものでもあったのである。このような読みかたや井上に対する評価はある意味で独善的なそれのようにも見えるが、読み手としての青木はもっとしたたかだろう。竹中宏論と関悦史論の間に井上弘美論を配置する青木であってみれば、自分の読みのありように無自覚であるはずがない。読む行為がはらむ本質的な傲慢さについて自覚的であろうとする青木を前にしたとき、僕は青木が井上のために一項をたてたことに誠実さを感じる。
本書の末尾を飾るのは関悦史論だが、同書を読んだとき「関悦史」を俳句史に残る存在として位置づけた青木の手腕に感嘆する者もあるかもしれない。しかし僕は「関悦史」を読む青木についてこのようにとらえている限り、青木の仕事の本質的な部分にはついに辿りつけないような気がする。「関悦史」が俳句史に残るか否かという議論はそんなに重要なことなのだろうか。僕が青木の関悦史論から感じたのはむしろ、「関悦史」が何よりもまず青木自身にとってそのように語らざるをえないほど重要なものであったらしいということであった。青木は関悦史論の冒頭で大竹伸朗が描いた「日本景」をとりあげ、次のように述べる。
歴史も奥行きも欠いた風景の中、私たちは大きな物語も信じられず、希望も悔恨も抱けないままあてどなく電柱を仰ぎ、郊外のモールやネットの中をさまようのみである。大竹の「日本景」は、この平成「日本」をデフォルメした作品だったといえよう。(略)
このよるべなき「日本」を、平成俳壇は片鱗でも詠みえただろうか。(略)混迷とジャンクのただ中で「既にそこにあるもの」を身近に感じ、慈しみ、昂ぶりとともに謳いえた平成俳人は、関悦史のほかに誰がいたであろうか。(「空爆と雑煮、既にそこにあった「平成」の道標」)
ここで青木は「私たち」と書きつけている。「関悦史」を読むということは、青木にとって、それを自らの詩としてひきとるということでもあったのだ。そして僕は読む行為における青木のこのようなありようこそ、青木の仕事の本質を示すものであると思う。
本書には随筆に近い文章も収められているが、たとえば青木はある随筆風の一編のなかで、自宅に掛けた虚子や碧梧桐の短冊への違和感から次のような認識に至ったことを率直に述べている。
聴秋や梅室などの宗匠の作品は、活字では平凡だが、暮らしの中で短冊や軸として接するといいしれぬ魅力を発する。聴秋たちの句は生活の平凡さを脅かさず、むしろ認めてくれるもので、だからこそ暮らしの中で魅力を放つのではないか。生活とは平凡であり、変わらぬ習慣とささやかな秩序に支えられた月並の別名に他ならないためだ。
しかし、虚子や碧梧桐の句はこうはいかない。彼らの作品には常識を揺るがす何かが潜んでおり、だからこそ「文学」として優れているとみなせよう。しかし、「文学」は生活の中で常に必要とされるものだろうか。(「日々暮らすこと、たとえば月並宗匠の書について」)
青木は自分と俳句との距離を測定するなかで、虚子や碧梧桐を遠ざけることさえ厭わない。「文学」なるものに対するこうした私的な実感に自覚的な青木の姿勢を端的に示しているのは、たとえば次の一文だろう。
なぜ、私たちは三森幹雄を否定せねばならないのだろう。幹雄率いる明倫講社は私たちの祖先かもしれないのである。私たちは天才でなく、凡人に過ぎない。(「俳諧宗匠、春秋庵幹雄」)
私たちは凡人に過ぎない―自らを凡人と称する者はこれまでにもいたことだろう。しかし、それを謙遜でも諧謔でもなく、悲壮感など微塵も伴わない率直な告白として披歴した者はどれだけいただろうか。
そういえば僕たちは、どういうわけか「天才」の姿ばかりを追いかけてきたのであった。俳句史のヒーローはいつも「天才」で、その「天才」の内実を問うことはあっても、僕たちはその「天才」を共有することの正義自体を問いなおすことはなかった。だから、たとえば俳句史が「天才」の群像とともに語られるとき、僕たちはあるいは恐縮し、あるいは自らの不出来を憂いては、その「天才」を畏れてきたのである。けれど、俳句史をそのように語る彼らのよって立つ正義など何だというのだろう。
「四Sや四Tばかりが相手じゃ曲がなく芸にならず飽き飽きする」と言ったのは加藤郁乎であったが(『俳の山なみ』角川学芸出版、二〇〇九)、僕たちはいまや加藤とは異なる意味において、四Sだの四Tだのそれらを語る俳句表現史的な文脈だのを、愛しつつも飽きてしまったのかもしれない。天才の営為は遠くから眺めてこそ美しいし、楽しいし、愛せもするけれど、その後に連なることはついに僕たちの切実な希求とはなりえないのではなかったか。ならば、僕たちはもっと僕たちのための読みをしていいはずなのである。そして、そのささやかな読みの向こうに想起される俳句史もまた信ずるに足るものであるはずなのである。