わたしの人生で大太鼓鳴らすひとよ何故いま連打するのだろうか 柳谷あゆみ
(『ダマスカスへ行く 前・後・途中』六花書林、2012年)
【ジェット噴射から始まる】
柳本々々(以下、Y): こんばんは、2016年最初の短詩時評です。今年はじめの短詩時評は同じ「かばん」会員でもある歌人の法橋ひらくさんをゲストにお招きして、ふたりが共通して好きな柳谷あゆみさんの歌集『ダマスカスへ行く 前・後・途中』のなかの一首について話し合ってみたいとおもいます。今回は新年初めということもあって少し羽を伸ばしてそんな自由な企画でやってみたいと思います。ひらくさん、よろしくお願いします。
法橋ひらく(以下、H): よろしくお願いします。2016年ってなんか字面だけでもすごい未来的なイメージなんですけど意外とまだ車が空飛んでたりはしなくて安心します(笑)。
Y: たしかにそうですよね、わたしもジェットパックを背中にしょってジェット噴射で空を飛んで歌会や句会に出かけたりする時代が2016年なのかなとか以前は思っていたんですが、ジェット噴射で窓辺から飛び立つにはあと10年くらいはかかるのかなと思っています。
H: あと10年でジェット噴射……!(笑)。
Y: …………!?
【大太鼓を鳴らすのは誰だ!?】
H: さてさて。柳谷さんの短歌、面白いですよね。ずっと前からファンなんですけど、じゃあどのくらい柳谷さんの短歌を読み解けているかというとそんなに自信もなくて、今日は柳本さんとの対談ということで色んなヒントや驚きをもらえそうで楽しみです。
Y: ええ、柳谷さんの短歌おもしろいですよね。私もファンなんです。ちなみに私が『かばん』に入会させていただいたきっかけは柳谷さんの短歌だったんです。このひとの短歌はなんだかとてつもないと。なんだか短歌がすごいことになっていると。いろんなびっくりがあったんです。先日ひらくさんとお話させていただいていたときにお互いが柳谷さんの短歌の話になってそこからきょうの対談をさせていただくことになりました。
H: あの日はなかなか盛り上がりましたね。今日取り上げるこの一首、柳谷さんらしさの炸裂した歌だと思うんですけど、柳本さんはどんな風に読まれていますか?
Y: そうですね、たしかに柳谷さんらしさを感じる短歌ですよね。まずこの短歌には〈「大太鼓鳴らすひと」っていうのは誰なんだ問題〉というのがあるように思うんですね。わたしはこの「大太鼓鳴らすひと」っていうのは〈外部〉にあるような「人生そのもの」或いは「神さま」みたいなものなんじゃないかとおもうんですよ。なにかこう、柳谷さんの短歌をみてるときにプラスティックの歌もそうなんですが(「ゆっくりとわかるのだろうほっとかれそのままでいるプラスティックを」)、自分ではいかんともしがたい・どうしようもない〈なにか〉がいつも〈このわたし〉をみつめている気がするんです。それこそ、柳谷さんの歌集のタイトルの言葉を借りれば、「ダマスカス」という〈外部〉がいつもわたしをみつめているとか。読み手も「ダマスカス」ってなんだろうって緊張感が歌集を読むときにあるように思うんですよ。なにしろたぶんこれから「ダマスカスへ行く」わけですから、そういうアトラクションに乗り込むような緊張感がある。だから〈人生のわけわかんない力〉がわたしには「大太鼓」のように思えるんですよ。
H: なるほど……早くも驚きの視点を提示していただきました。柳本さんはこの一首の中の〈ひと〉を人間ではない、運命的な不可視のチカラとして読んでらっしゃるんですね。
Y: そうなんです。なにか柳谷さんの短歌っていつも〈得体のしれない大きなちから〉と向き合っている感じがするんですよ。タイトルの「ダマスカス」も決して「地名」だけでなくて、そうした〈得体のしれない大きなちから〉という感じがします。そうした〈大きなちから〉のなかに入っていくのが「ダマスカスへ行く」ことなのかなって。ひらくさんはどう思われましたか。
H: 僕はこの歌、恋愛の絡んだ歌かと思って読んでいました。かつてとても好きだったひと、消化しきれない感情を抱いている相手のことを〈わたしの人生で大太鼓鳴らすひと〉と呼んでいるのかと。
Y: あ、それだとぜんぜん違った視点でおもしろいですね。恋愛かあ。恋の歌ですね。
H: 多分、今はもう何の関係性があるわけでもないのだけど、自分の人生史上でのその相手の存在の大きさはどうにも無視できなくて、それはまるで大太鼓を鳴らされているかのようだという……そんな風に読んで(わかるなあ)なんて思っていました。
Y: なるほど。ひらくさんの短歌にもよく〈記憶〉のテーマが出てくるんだけれども、なにかこう〈記憶〉を抑圧していて、思い出さないようにしているんだけれど、その思い出さないようにしていることそのものが揺り動かされるかんじですよね。記憶の大太鼓、というか。
H: まさにそんなイメージかもしれません。あるいは、抑圧したつもりのない自然に薄れた記憶であっても、無意識の海からふいに還ってくることもありますしね。〈何故いま連打するのだろうか〉という下句、少なからず主体は苛立っていますよね。何かのきっかけで、例えばかつての恋人の近況を偶然耳にしたとかそんな場合に、その相手に対峙したときの自己価値の不安定さ──影響される側、動揺させられる側である自分──を再認識してしまったことへの苛立ちがここには表れているんじゃないかなぁと感じるんです。相手に対する自分の弱さを感じているという点では、〈人生のわけわかんない力〉に対峙する〈私〉という構図も同じですね。
Y: そうか、たしかに恋愛とか記憶って、〈じぶんがどうにもできない巨大なちから〉と向き合うことにもどこか近いですよね。ある意味で、恋愛とか記憶ってそういう〈人生のわけわかんない力〉に向き合いつづけることですもんね。ひらくさんの歌集のタイトルが『それはとても速くて永い』というすごく印象的なタイトルで、私は〈記憶〉のテーマを一文にまとめられたような印象がしたのですが、なにかこう柳谷さんのこの大太鼓の短歌はそのタイトルを裏返したような、〈それはとても遅くて短い〉というような、〈なぜ今なんだよ!〉というひらくさんのおっしゃった〈苛立ち〉のようなものもあるのかもしれないなと感じました。
H: それはとても遅くて短い……(笑)。見事に裏返しですね。でも確かに、この歌に描かれている状況はその通りですね。
Y: ええ(笑)。ひらくさんの歌集のタイトルがそもそも〈時間〉との関わりがとても深いと思うんだけれども、柳谷さんの歌集もサブタイトルに「前・後・途中」とあるように〈時間〉との関わりを読者に示唆していると思うんですよね。
【恋と神】
Y: で、この短歌で次にわたしが気になっているというか、ひらくさんにお聞きしてみたいのが「連打」という言葉の選択です。よくゲームでボタンを連打するっていう言い回しがあるけれど、どこかこの歌には〈ゲーム性〉のようなものがあるんじゃないかと思うんですよね。柳谷さんの歌集に「シャイとかは問題ではない一晩中死なないマリオの前進を見た」っていう歌があるんだけれども、そこでは「マリオ」の〈人生〉が歌われている。「シャイ」っていう〈内面〉なんて問題じゃないんだ。「死なないマリオの前進」というゲームリアリズムのなかの〈無敵〉が大事なんだっていう、ちょっとこれもどこかで「神さま」と通じているような歌でもあると思うんですよ。「神さま」って言ってますが、宗教的な意味ではなく、超越性というか、わたしを大きな世界からみている〈誰か〉です。そういう〈誰か〉がいるんだってことがわかっている。でもその〈誰か〉にひれふすわけじゃなくて、「何故いま連打するのだろうか」とこちらから問いかけたりもする。そういう訴えることもできる「神さま」です。
H: そう、〈連打する〉この言い回しも絶妙ですよね。まさに柳谷節って感じがします。連打するというからにはそこにはある程度の〈経過する時間〉があるわけで、音楽で言えばサビにあたるようなそんな盛り上がったひとまとまりの時間のイメージでしょうか。そしてここにはその〈経過する時間〉にじっと耐えている、やり過ごそうとしている主体の姿があるように感じます。柳本さんの読みでは、〈やり過ごす〉というよりも、より積極的に〈問いかけて〉いる主体の像が結ばれますね。
Y: ええ。そこをどうとるかで読み手の位置も変わってくるかもしれませんね。恋愛ベクトルだと〈やり過ごす〉主体になってくるかもしれないし、そういう読み手が関わりながらこの大太鼓を受ける主体を成立させていく短歌なのかもしれない。つまり歌は読み手にもこう言っている。おまえも連打しなさい、この太鼓(歌)を。
H: なるほど。じゃあ僕はその呼びかけに答えるカタチでこの歌を<恋の歌>だと読んだわけですね……歌会とかでよく「ひらくはロマンチストだね」って言われるんですけどやっぱそうなのかな(笑)。ここらへん、特定の他者を相手とするか「神さま」を相手とするかによって読みのバラけてくる部分かもしれませんね。
Y: そうなってきますね。
H: そういう意味では神さまってやっぱり優しい存在ですよね。こちらが求める限りいつまでも打ち切られることなく対話できるわけですから。……話が逸れましたけど。
Y: あ、そうか。たしかに。神さまって〈沈黙〉が〈饒舌〉になる存在だから(祈りは通じるし神さまはきっと最後には答えてくれる)、たとえば片想いの恋愛相手とちょっとその点似通ってはいるんだけれども、でも神さまが一切肯定(わたしにイエスといってくれる)が多いのに対して、恋愛相手はこのわたしを記憶の底からでもたたきのめすことがありますよね(わたしにノーをつきつけてくる)。そこらへんはベクトルが変わってきますね。〈だれ〉とむきあっているかで。
【決意の一閃】
Y: で、ですね。この短歌でもうひとつ気になったのが、時間分節というか、先ほどもお話しましたが、ひらくさんの歌集のタイトルが『それはとても速くて永い』という〈時間〉を想起させるようなタイトルになっているのだけれど、柳谷さんの歌集にもサブタイトルに「前・後・途中」っていう〈時間〉が刻印されているんですね。前もって時間のプロセスを読み手がかいくぐっていくことが予期されている。「大太鼓」の歌も〈大太鼓の連打〉によって人生が区切られていく、そういう〈区分ソング〉ということもできるんじゃないかとおもうんですよ。神さま、わたしの区分はこっちです! という主張というか。「大太鼓」なので相手も本気でこっちを区分しようとしているけれど、いやそうじゃないんだ、わたしの大太鼓はもっと後にあるんだというか。そういう意味では〈プロテストソング〉でもある。
H: 区分ということについては僕はそこまで思いが至らなかったのだけど、プロテストソング、というのは面白いですね。それはすごく本質を突いているような気がします。柳本さんのおっしゃる〈何か大きな外部的存在への問いかけ〉という意味でもそうですし、恋愛の絡んだ歌なんじゃないかという僕の読みにおいても〈内側で揺らぎそうになる自己価値へのプロテスト〉という意味では同じですね。外に向くか、内に向かうかのベクトルの違いはあれど。大太鼓っていう道具立ても重要なのかな。例えばもし、ここで演奏されている楽器がフルートだったりしたら、フラ~っとついていきたくなっちゃうかも(笑)。
Y: フルートだったら(笑)。あ、そうか。そういう楽器視点で考えるのは、おもしろい! この歌の楽器が「大太鼓」であるのがたしかに重要ですね。ひらくさんがおっしゃるようにフルートやタンバリンだったらとつぜん自分をもっていかれない感じはあるんだけれど、「大太鼓」だともう有無をいえない感じがある。どこどこどこどこどこどこどこどこ叩かれては、言葉も意志も思想も太刀打ちできないですね。楽器の音律にのって歌うわけにもいかないし、踊るわけにもいかない。鳴らしているのを無理に止めようとしても、反撃されて「ばち」で叩かれそうじゃないですか。笛とかでたたかれてもだいじょうぶそうだけれど、ばちだとすごく治療に時間がかかりそうなので。痛そうですよね。そういう「大太鼓」って武器のイメージがあるんです。トルコの軍楽隊が太鼓を打ち鳴らしていたり、戦争と太鼓ってたぶん関係が深いと思うんだけれど(ちょっと太宰治の「トカトントン」も思い出しますが)、どこか戦争のイメージもまとっている歌なのかもしれないなとおもってしまう。
H: 太鼓と戦争、かぁ……言われてみれば確かに、大型の太鼓っていうのは洋の東西を問わず〈勇猛さ〉の表現として演奏されやすい楽器ですね。
Y: ああ、そうですね。行進とか前進の楽器ですもんね。
H: 勇猛さを保証するのは決意の強さだと思うので、その意味では大太鼓っていうのは〈決意〉の象徴なのかもしれない。
Y: うんうん。
H: 演奏スタイルから言っても、大太鼓やシンバルなんかを叩くのにはある種の瞬間的な決意が要りますもんね。
Y: なるほど! 決意や瞬間の楽器なんですね。
H: そう考えると、この歌の大太鼓を連打されている状況というのは〈自分の決意を問われている〉感覚の表現なのかもしれませんね。プロテストのためのプロテスト、ではなくて、何らかの決意を固めるまでの時間稼ぎとしてのプロテスト、なのかもしれません。
【それぞれの〈ダマスカス〉】
Y: そうか、いままでひらくさんのお話をうかがってきてわかったのですが、この柳谷さんの一首って〈決意の歌〉でもあるんですね。いま大太鼓鳴らされてる、だったらわたしはわたしの大太鼓を鳴らして決めなきゃ! でないと決められてしまう、っていう。だからあっちから時間分節されないで、このわたしがこの瞬間を決めるんだっていう〈決意と瞬間の一首〉になっている。2016年、〈決意の瞬間〉を求められるたびにこの柳谷さんの一首を思い出してみようと思います。
H: 〈決意と瞬間の一首〉。なんかすごくカッコよく決まりましたね。そのフレーズ欲しいな……(笑)。そう、で、この瞬間を決める決意というのは「自分のことは全部自分で決める」という頑なさのことではなくて、どうしようもない大きな力による誘いをどんな風に受け入れるか、あるいはどんな風に受け入れずにいるかという〈意志〉のことなんでしょうね。自我を最上位に置かない意志というか。この感じが柳谷さんの持ち味なのかなという気がしてきました。
Y: ああ、なるほど。柳谷さんの歌集にはサブタイトルに「前・後・途中」と付けてあったけれど、まさにそういう〈自我の向こう側〉にあるコントロールできない〈時間〉のプロセスを楽しもうという感じもありますよね。たとえば「ダマスカス」は決して自分の支配できる領域にはならないんだけれど、でも、その〈支配できなさ〉のプロセスを逆に楽しんでしまうというか。それが〈生きる〉ってことでしょう、っていう。めいめいが持って生きていかなければならない〈ダマスカス〉ってあるわけですからね。私も「ダマスカス」には行ったことはないけれど、でも私が生きなければいけない〈ダマスカス〉はある。それはコントロールできないものとして。しかし、その過程を楽しむものとして。
H: そっか。割と自分、コントロール欲求の強い方なので、それで柳谷さんの短歌に惹かれるのかもしれないなぁといま柳本さんのお話を聞きながら思いました。誰の中にもある<ダマスカス>、良いですね。僕にとっては何だろうな……。たくさん話しましたけど、こうやってお互いの読みを共有しあうとなんか深まっていく感じがすごいですね。
Y: ほんとうにそうですね! 一首だけを徹底的に話し合うってなかなかない機会だと思うけれど、たった一首でも〈それぞれの読みの立場〉に立ってみることでいろんな歌の読みの可能性が相互作用でひらけてくるということがわかりました。この歌集の〈ダマスカス〉のような、価値観が違うもの同士が集いながら価値をすり合わせ相互作用によって言語感覚を新しく更新していく場所。〈読みの場所〉というものもそういうふうにあるものかもしれませんね。短歌というものは、一首が成立したあとから、〈短歌の読み〉が次から次へと生まれてくるものではあるけれど、でもその〈短歌の読み〉をめぐる〈時間〉というのも、ある意味では〈それはとても速くて永い〉し、また一方では〈それはとても遅くて短い〉ものでもあるかもしれないなと思いました。〈永遠と、いっしゅん〉のなかにずっと〈短歌の読み〉はある。きょうはひらくさんからいいお話をいただきました。ほんとうにありがとうございました!
H: いえいえ、こちらこそです! 予想していた通り、柳本さんとの対談、とても刺激的でした。面白かったぁ。ありがとうございました!
Y: 最後にひらくさんにひらくさんご自身の短歌からの自選歌五首をお願いしました。今回は歌集刊行以降の歌から選んでくださったそうです。
H: 自選歌、歌集からはどうも決めきれなかったので、歌集刊行以降の歌から今の気分で5つ選んで、それとなく連作っぽくも読めるような順番で並べてみました。今の自分の気分はなんかこう、字幕なしで外国の映画をぼんやり観てるみたいな、そういう感じに惹かれてるみたいです。
Y: 「字幕なしで外国の映画をみてるみたいな」ってすごくよい言葉ですね。たぶんそれは純粋に〈ひかり〉を感じているってことなんじゃないかと思うんですよね。言葉、でもなくて。映画って、ひかりですもんね。そして〈ひかり〉っていつも〈いま・ここ〉に満ちているものですよね。読ませていただいたのですが全体的に「ひかり」に満ちていて、ひらくさんの短歌の新しい質感を感じ取れるとてもすてきな連作になっていると思いました。新春にふさわしい短歌を最後にいただいたと思います。きょうはほんとうにありがとうございました。
【法橋ひらくさんの自選歌五首】
寝たふりの後部座席でわかってた(もう着くんだね)光でわかる
アンニュイは春の季語かもしれないね染谷将太が老けていっても
それからの話もしようこれからは語尾に「けど」とか付けずにもっと
こぼれそうな青いひかりに指をあてずっと見ている夜、熱帯魚
幸せな気分でいるよ五年後の夏の陽射しの中であなたは





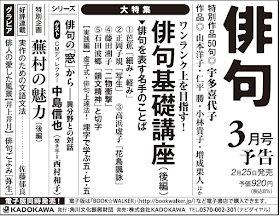






 ※掲載開始 2015年10月2日
※掲載開始 2015年10月2日